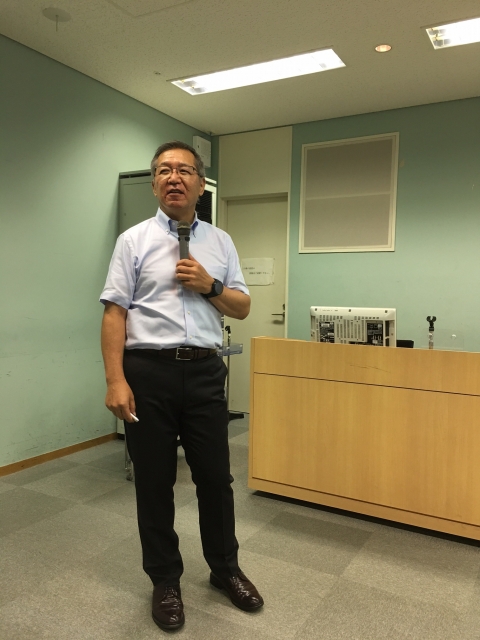- ホーム>ブログ


先月のブログ更新数を超えた今日の一本!
このブログ更新で、先月の数を超えた!
万歳!と喜んでばかりはいられない。
なにせ、このめまぐるしい毎日の中、ブログ更新ばかりを気にしながら
仕事をしているような、部外者お人が聞けば、施設長としての資質を問われかねない。
いや、いや、施設長として、協議会の役員として、お福の会の発起人の一人として・・・・・云々
しっかりと役割は遂行していますよ!(笑)
さて、このブログで皆さんに伝えたいこと。
それは今朝方の一人の職員からの手紙にあるのです。
いつもお話しているように、うちの太陽の家では、月一回、全職員さんから
前月の自己評価と次月の目標設定を書いて提出してもらっています。
その用紙には、毎回、自己評価を施設長が読ませてもらって、それぞれの考え方に
私なりの意見やアドバイスを記入して返却しています。言うなれば、職員と僕の月一回の交換日記みたいなものです。
さて、その自己評価にあわせて、ある職員から注意書きが挿入されていました。
内容は、最近のデイサービスの利用者数が減少する状況に僕の顔つきが険しくなってきているという内容でした。
そしてその職員は、太陽の家に係わる人々、職員も利用者も合わせて、その人たちは僕の顔色に注視している。
施設の雰囲気は、僕の顔色を写す鏡だ!と言う厳しい言葉でした。
恥も外聞も捨てて、その文面を読んだ僕の気持ちを言い表せば
とても嬉しかった!と言うのが正直な本音です。
世間一般的に、このようなメッセージを受け取った上司と言われる立場の人たちはどのように思うのでしょうね?
社会一般の思いなど別にして、僕はやはり、このような関係は喜ばしいと考えている。
そして、正直に自分自身が気づいていないことを指摘してくれる職員に一本取られた!と思うのです。
ただ言い訳になるかもしれないのですが、本音の部分でいえばデイサービスの利用者数の減少もつらいのですが
それよりも、今一番僕を苦しめているのが、次の新設法人の立ち上げに関する悩みが一番大きいのです。
こんな苦労して何になる?と自分に問う毎日ですが、それでも、やはり今やらなければ!いつやるの?と思うのです。
だから毎日、針の筵の上を、必死に地ならししている状況です。
しかし、それだから僕の顔から笑顔が少なくなった言い訳にはなりませんよね!!!!
自分の気分を外に出さない。その思いに変わりなかったはずですが
少し自分自身、甘えていたようです。
痛烈な一発でした!!(笑)
職員との意見交換において
認知症ケアを専門に行う職員との意見交換は定期的に行うべきだと感じた。
認知症ケアにあたり、専門職と言われる以上、そのBPSDへの対処には専門職なりの接遇を習得すべきことは言うまでもない、
また、チームでケアに当たることの重要性も伝えてきた。
しかし、相手も人間であると同時に、対応する我々も人間である。
特に夜間の一人夜勤の体制の時は、そのストレスは想像以上の負荷がかかるようである。
そりゃ、認知症の人だから 意思の疎通が困難であり、真摯な態度で説明し不安を取り除いても
その効果は数分しか継続できず
納得した数分後には、また同じ不安感の訴えが繰り返される。
人によっては、その行動が一晩中繰り返される。
夜だけでなく、昼間も元気いっぱい、この人はいつ寝るんだろう????と逆に心配になるような
異常な体力の持ち主。ひょっとすると、この方には正常な人にはないアドレナリン等の脳の刺激伝達物質が夜昼関係なく
体力の続く限り毎日放出され続けているのかもしれない。
この異常な体内時計の混乱に対応するために眠剤を投与することで
夜間の転倒リスクも急激に高まる。この年齢で転倒は寝たきり指数をアップさせてしまう。
結果的に薬での対処は無用である。そうなるとやはり、人としての支援しか方法はなくなってしまう。
繰り返しの訴えに、繰り返しの応答の連続しかしようがない。
夜間にしっかりと寝てもらうために狂った体内時計の調整を昼間行う。
そのためには、昼間にしっかりと日光を浴びてもらう。
日中の活動量を増やす。
出来る限りの不安要素を排除する。
考えられることはすべて試してみること。そして、次に大事なことは
入居者家族と十分すぎるといわれるまで意見交換を行うこと。
さらに大事なことは、そんなストレスを抱える職員の精神を同僚、管理者、経営者がしっかりと理解すること。
介護している中で、理屈は分かっていたとしても、瞬間的に虐待や殺人等の気持ちが脳裏を横切る現実があることを
上司は理解すべきである。だからと言って、僕は虐待や殺人などの行為を理解するつもりはないし
どのような理由であれ認めることはできない。
ただ、そのような極限に追いつめられることもあるのが、認知症介護であることは理解している。
そのような極限の場での事件や事故を未然に防いでいく為には
経営者、管理者並びに同僚を含め施設ぐるみで、そのようなストレスから職員や利用者個人を守っていかなくてはならない。
そのために何をすべきか?個々のポイントが良い経営者になるか、悪い経営者になるかの瀬戸際である。
太陽の家納涼夏祭り
昨日は、太陽の家納涼夏祭りを開催しました。
家族さんにもお越しいただくとよいのですが
駐車場やデイルームのスペースの問題もあり
家族さんを交えての開催はできませんでした。
夏祭りを演出するために紅白幕を張り巡らし
昔懐かしい射的、ビニールプールからヨーヨー釣り、
綿菓子にベビーカステラを食べていただきました。
昼食には、炭火で焼く日干しの魚をメインに
おいしくお昼ご飯を召し上がっていただきました。
8月研修会終了後の懇親会です。
ここ数年、研修や懇親会への参加者が低迷しているのですが
先月の和田行男氏を囲んで行った懇親会に続き
今回の研修終了後の懇親会です。
今夜は津の「東洋軒」で行いました。
うちの協議会では、酒飲みが少なく、かく言う私自身も酒を好まない体質ですので
自ずと飲み会の類とは縁遠い体質があります。
また、三重県内でも遠方から参加する会員さんも多く、
酒を飲んで帰宅するには、あまりにも遠すぎ
タクシーや公共交通機関を利用するのも限度があり
懇親会に参加することも厳しくなってきたようです。
もちろん、飲酒運転の罰則が強化されたから呑まなくなったというわけでもなく
研修に引き続き懇親会まで付き合うことで、施設を離れる時間が長時間化することも
参加率の低迷にはありそうですね。
この協議会が組織化された当初の頃は、忘年会も開催されており
鳥羽のホテルで一泊どまりで開催し、80人ほどの参加者が大宴会場に勢ぞろいした時もあったのです。
もう今から10数年前の話ではありますが。
時の変化と社会情勢の変化ってのは、本当に人々の行動に影響を及ぼすものですね。
今日は三重県総合文化センターにて定例研修の日です。
今日は三重県地域密着型サービス協議会 8月度研修の日です。
ゲスト講師に高齢者総合福祉施設アザレアンさなだ、総合施設長の宮島渡先生をお招きして
「施策としての認知症ケアと批准」~地域密着型サービスの現状と課題~をテーマに
講演をしていただきました。
正直、とても新鮮な気分になり、認知症ケアを学びなおせた気分でした。
宮島先生は、大府認知症研究研修センターでの認知症介護指導者養成研修にて
お世話になった方です。
大府センターでは、入校二日目の授業で丸一日かけて、ご指導いただいたのですが
今回は、認知症グループホームの将来、危ないぜ!と、認知症専門職としてのポジションを
更に社会全体にアピールしていかなければいけない。と注意喚起されました。
認知症の人が、専門性を追求されることなく、サ高住、有料老人ホームに流れてしまうのは
グループホームでなくても何ら支障はないとの印象が強すぎる。
つまりは、役割を認識できていないグループホームの事業者が多すぎる!と言われます。
確かに、認知症の人の余生は、グループホーム事業者の手にかかっていない。そのような
理解しか一般社会には提供できていない。そのことが、自分で自分の首を絞めている現状を
もっと事業者自身が認識すべきであるということです。
宮島先生に限らず、この問題は、多くの有識者が語っているグループホームの現状です。
入居させれば完結するグループホームの事業目的では、
社会全体にグループホームの存在をアピールすることはできないし、
そこにグループホームの存在理由がなくなる。
色々な活動をしている、地域との連携は保たれている、認知症カフェをやっている。
そんなPR 合戦に重きを置き、そこに提供されているケアがマヤカシでは
グループホームなんて必要ないのです。
認知症の専門職として、入居者のBPSDを課題とすること自体が
自らのサービスの脆弱性と無能ぶりを公言しているようなものだ!と
僕も常日頃より思っている。
認知症をしっかりと理解し、その人の病気に対応できる洞察力を磨くことが
今後のグループホームの事業者にとって、とても重要かつ大変なところだと感じました。








 「
「